
やきもちを焼いてしまう
彼は友達が多かった。
誰かと彼が仲良さそうに話しているだけで、腹が立った。
そう、やきもち。
あんなに楽しそうに何を話してるんだろう。その相手が何で僕じゃないんだろう、って思ってしまうぐらい僕は彼に恋をしていた。
そんな僕をみて彼に、「なんか怒ってる?」ってよく聞かれた。
「怒ってない。」
「いや、怒ってる。」
「怒ってない・・・。」
「うそつけ。」
だってあなたが悪いんです。僕じゃなくてだれかと楽しそうにしてるから。今思うと、なんて自分勝手な思いなんだろうと思います。
「やきもちやくな。」
「そんなわけないやろ。」
「顔見たらわかるわ。でも、ちゃんとお前のとこ戻ってきたやろ。」
そういって彼に頬をつねられる。
僕は自分でも顔が真っ赤になるのが分かった。
それを見てまた彼が笑ってる。
アイスクリームも溶けるほど
僕が怒ってても、ただ彼は笑って僕をからかうように話しかけてきた。
そんな時、僕の手が彼の手に当たって彼が持っていたアイスクリームが地面に落ちた。
「ごめん」
やっと謝れた僕。
「また買ったらええから気にすんな。売店いこか。」って。
いつでも優しかった。
ある時、彼に言われたことがある。
「お前は、存在が近くになったと思ったら、すぐに遠くにいくな」と。
僕だって本当はもっと何でも話したかったし、近いままでいたかった。でも、彼への好きな気持ちがバレちゃいそうで怖かったし、自分の本質を素直に話すわけにはいかなった。
そう、自分がゲイだなんて絶対言えない。
バレたらもう一緒になんかいられない。
絶対に嫌われる。
だから近くになりすぎるのを、僕はいつも自分から拒んだ。
僕に触れる彼を
彼はなんでかたまに僕に触れた。
夏、真っ黒に日焼けして腕の皮が剥けてたら、僕の腕をぎゅっと掴んで「俺が皮むいたろ。」
と僕の腕をずっと握ってたり。
電車で横並びで座ると、足を思い切り開いて僕にくっつけたり。
僕が「狭い」っていっても「うるさい」っていってずっとくっついていた。
でもそうやって彼に少しでも触れていられるのがうれしかった。
彼もゲイなのかな。
僕が彼に触れたいって思うのと同じように、彼もそう思ってくれてるのかな。
まさかね・・・
ずっとこんな時間が続けば良いのにって思ってた。
でも、そうはならなかった。
同じ大学には行けない
僕らは高校3年生。
もう受験が待っていた。
彼と離れ離れになるのか・・・
彼は頭がよかった。
僕は偏差値的に彼と同じ大学にいくのは無理だった。
そもそも僕は大学に興味はなかった。映画や音楽にしか興味がなかった僕は、専門学校に行きたかった。
彼と一緒にいられなくなるのかなっていう思いと、自分の将来への不安。いろいろ混ざって何を選べばいいかわからなくなっていた。
「お前が何かしたいことあるんやったら、俺も一緒にやるぞ」
なんでだろう、彼には僕の不安とかがわかるのか、何もそんなこといってないのに。
そんなことをサラッといえる彼がうらやましかった。
何にもない空っぽな僕は、彼に何の返答もできなかった。



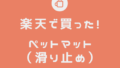
コメント